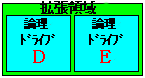
[第2ハードディスク 例 SCSIディスク]
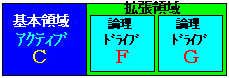
ドライブレターの詳細
基本領域が先ということは、たとえ第一ハードディスクに基本領域がない場合でもちゃんと適用される。従って次ぎのようなケースの場合も基本領域が先にドライブレターがふられる。
[第1ハードディスク 例
IDEディスク(拡張領域のみ)]
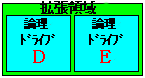
[第2ハードディスク 例
SCSIディスク]
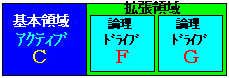
これを見るとこの性質(基本領域が先)を利用して、たとえSCSIを先にできない古いマザーボードでもSCSIドライブを起動ドライブにできるように見える。しかし残念ながらこれはできない。上記のような構成した場合、確かにフロッピー起動すれば、上記のようなドライブ順になることが確認できるが、実は上記のCドライブからはOSを起動することができない。
PC/AT互換機の一般仕様では、第1ハードディスクのアクティブな基本領域からしか起動できないので、BIOSは第1ハードディスクにアクティブな基本領域を発見できなかった時点でブートをやめてしまう。以降第2ハードディスクをスキャンしたりはしない。
基本的にWindows95/98などのFDISKでは複数の基本領域は作れないので、通常のWindows95/98ユーザには関係ないことだが、WindowsNTのディスクアドミニストレータやLinuxのFdiskなどでは、複数の基本領域を作れるので、その場合どのようなドライブレターになるか見てみよう。
結論から言うと、複数の基本領域がある場合、アクティブな領域が先になる。それ以上に興味深いのはアクティブでない基本領域は、論理ドライブよりも後になってしまう。具体的には次ぎのようになる。
[複数の基本領域]
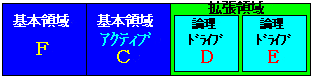
このアクティブが先になるという性質を利用して、ちょっと面倒だが、アクティブを切り替えて複数のOSをマルチブートするということもできる。
更に複数のアクティブな基本領域があったらどうなるでしょう。これは前にも説明したようにPC/AT互換機の一般仕様では基本的に違反で、NTのディスクアドミニストレータでも設定することはできない。Linuxのfdiskでは設定可能だ。
[複数のアクティブ基本領域]
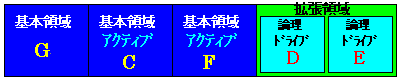
この場合、先頭のアクティブ基本領域のみ、アクティブ基本領域と認められた動作になる。つまり先頭以外のアクティブ基本領域は、非アクティブ基本領域同様、拡張領域よりも後まわしになる。ただし同一ハードディスク内では非アクティブ基本領域よりは先になり、アクティブであることの効果がでているようだ。
更に基本領域があってもアクティブなものが一つも無かった場合はどうだろう。
[複数の非アクティブ基本領域]
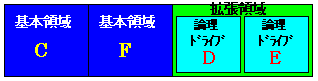
この場合でもやはり、先頭の基本領域は論理領域よりも先になる。結局基本が先、論理が後という単純なものではないことが分かるだろう。整理すると以下のようになるようだ。
論理領域内では、チェーン構造に沿ってふられ、3番、4番で同じタイプ同士の場合、前の方のパーティションが先になる。また今まで「先頭」とか「前」と言っているのは、ハードディスク上の物理的位置ではなくて、パーティションテーブルのエントリ位置のことを指す。
また以上は、あくまで全ての領域を起動したOSが知っている場合で、もしパーティションの中にそのOSが知らない領域があった場合、その領域はあたかも無かったかのように扱われて、ドライブレターが振られる。
知らない領域とは、たとえばWindows95初期型にとってのFAT32や、Windows95/98にとってのNTFSなどを指します。逆に知っている領域以外の全てと言った方が適切だろう。ただしWindowsNT 4.0では、FAT32は理解できないのだが、知らない領域ではなく、ドライブレターが振られることに注意してほしい。図示すると以下のようになる。
[知らない領域がある場合]
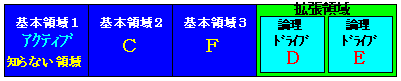
この例では先頭のアクティブ基本領域が知らない領域なので、あたかも無いかのように扱われ、前述の複数の非アクティブ基本領域がある場合と同じになる。
[第1ハードディスク]
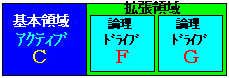
[第2ハードディスク]
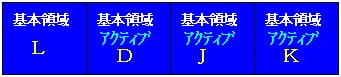
[第3ハードディスク]
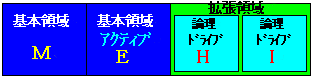
まあ普通はこんな構成にはしないと思うので、あくまで参考ということで。
因みにこれにMOなどが加わるとWindows NTの場合、もっと複雑になる。MOもFDISKフォーマットでき、この場合アクティブ基本領域と同等に扱われるので、上記のドライブレター順に割り込んでくる。NTではMOが予期しない若いドライブレターになって困った経験がある人は少なくないだろう。幸いWindows95/98の場合はSCSI機器の認識がIDEより後になるので、この問題は起こらない。